こんにちは!ちゃちゃです。
実は、もうすぐ退職します。
具体的には2022年8月末をもって、退職予定です。

退職後の手続き、大変そう……
何をすればいいんだろう??
↑今の私の素直な気持ち。(笑)
今回の記事では、退職後の手続きについてまとめます。
実際に体験したら、体験談も追加していきますね。
退職後の予定

退職後はすぐには働かず、仕事を探しながら
自由な時間を過ごそうと考えています!
調べてみると、退職後にすぐに働く方は、手続きが簡単。
全体を新しい会社で引き続きお願いすればいいですもんね。

すぐに働かない私は、手続きが色々あるようです……
ひとつひとつ、頑張ります!
退職時の私の状況とお願い
退職時の状況
前提が違うと手続きが変わる部分があるので、
まずは私の状況を整理しておきます。
- 30代独身
- ひとり暮らし
- 退職後はとりあえず実家に戻る予定
この記事におけるお願い
今回の退職後の手続きの流れは、
2022年6月に私が調べた情報です。
自分事でもあるので、入念なリサーチをしていますが、
間違っていないとは言い切れません。
あくまでも参考でお願いします。
退職後に必要な手続き4つ
退職後に必要な手続きは4つあり、
住民税・失業保険・年金・健康保険です。
それぞれ手続き内容や期限を整理します。
住民税
住民税は、1月~5月に退職する場合と、
6月~12月に退職する場合で異なります。
私は8月末退職なので、後者です。
具体的には、2つの選択肢から選べます。
1)翌年の5月までの分を最後の給与から一括で天引き
退職予定の会社の人事に、事前にお願いする必要があります。
2)3ヵ月ごとに普通徴収
この場合は手続き不要のようです。

1)と 2)で納める金額は変わらないようなので、手続きの不要な
2)3ヵ月ごとに普通徴収を選択するつもりです。
そもそも住民税は、「後払い」です。
すなわち、2021年1月~12月分を2022年6月~2023年5月に支払います。
2022年8月末に退職しても、2022年の分の支払いが
2023年6月~2024年5月まで続くんですね。
なんだか果てしない感じがしますが、しっかり納税します。
失業保険
失業保険を受け取るには、居住地のハローワークで手続きが必要です。
手続きの期限はありませんが、
手続きが遅れるほど失業保険をもらえる時期も遅くなるので、
早めの手続きが良いでしょう。
手続きに必要な「離職票」は、退職日の10日後頃に会社から届きます。

離職票が届きしだい、
ハローワークに手続きに行ってきます。
年金
私の場合は、国民年金に切り替えが必要です。

退職日の翌日から14日以内に、
役所の国民年金窓口で手続きします。
国民年金への切り替えのほかに、
家族の扶養に入るという選択肢もあります。
健康保険
健康保険は、任意継続する予定です。
任意継続は、退職する会社の健康保険に
最大2年間入り続けられる制度。
退職日の翌日から20日以内に会社に申請します。
保険料は会社負担分も支払うので2倍になると言われていますが、
上限額があるのでそんなに高くなさそうです。
実際の額が分かったら、まとめます!
任意継続以外の選択肢は、2つ。
・国民健康保険に切り替え(退職日の翌日から14日以内)
・家族の扶養に入る(なるべく早く)

保険料は、家族の状況や年齢、
お住まいの地域によって異なるので確認しましょう。
- ・任意継続の場合 ⇒ 退職予定の会社へ問い合わせ
- ・国民健康保険に切り替える場合 ⇒ お住まいの役所へ問い合わせ
- ・家族の扶養に入る ⇒ 無料
退職後の流れを理解して早めの手続きをしよう

退職後の手続き4つを整理しました。

調べ始めたときはチンプンカンプンでしたが、
少しずつ分かってきて一歩前進!
ギリギリに焦らないように、早めの手続きを心がけます!
さらに12月31日時点で無職の場合は、確定申告が必要。
会社を退職すると、色々大変ですね……
ここまで読んでくださり、ありがとうございました!
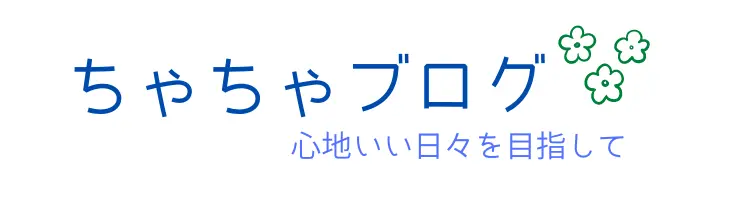

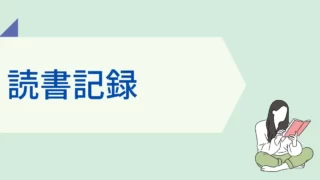
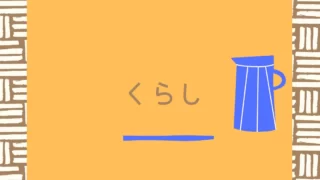

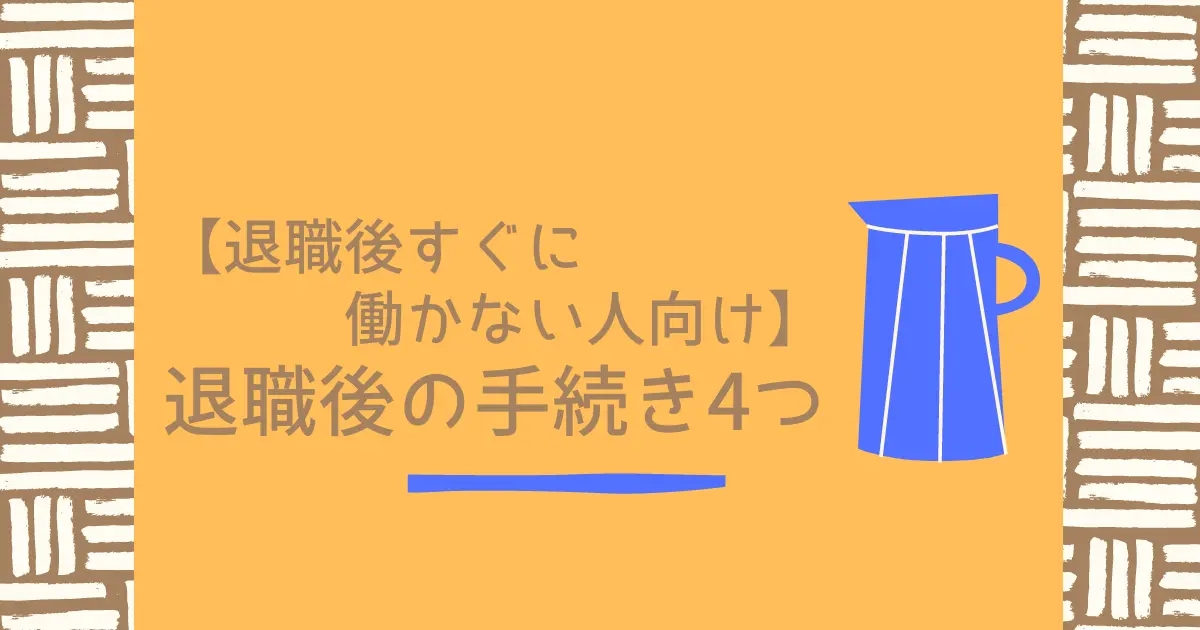

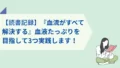
コメント